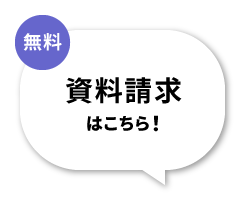株式会社ダイナックスは、北海道に本社を置き、自動車用のクラッチ用ディスクやプレートなどを生産する企業です。
『未来を今に』というモットーのもと、自動車用駆動系専門メーカーとして創業から50年間最前線を走っています。
今回は、株式会社ダイナックスの安全衛生管理部に所属する福島様・高谷様にお話を伺いました。
| 目的 | 教育・研修の習熟度アップ |
|---|---|
| 用途 | 安全研修VRコンテンツ編集(360度動画) |
| 業種 | 製造業 |
| 会社名 | 株式会社ダイナックス |
|---|---|
| 所在地 | 北海道千歳市上長都1053番地1(本社) |
| 事業内容 | 乗用車・商用車並びに産業用・建設機械用・船舶用の湿式摩擦材、プレート等、摩擦機能部品の製造販売 |
| URL | https://www.dynax-j.com/ja/ |
過去に発生した労働災害をVRで再現
– はじめに、御社とVR使用部署のご紹介をお願いします。
ダイナックス様:
弊社は自動車のクラッチ用ディスク、クラッチ用プレートや、シンクロナイザリングと呼ばれる部品など自動車の摩擦部品や、研削機部品を製造しています。
国内の自動車メーカーだけでなく、海外の大手の自動車メーカーとも取引があり、小型EV(電気自動車)の駆動モーターの開発なども行っています。

私達の所属する安全衛生管理部は、弊社の基本理念である「安全は全てに優先する、安全第一」のもと会社の安全衛生・防火を管理推進しており、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)を活用して、ゼロ災害の職場づくりを目指して各種活動を行っています。

安全衛生管理部には現在8名が所属しており、日々の安全パトロールや、法令遵守のための活動、今は労働災害(以下「災害」)の未然防止活動に力を入れています。
今の時期だと、弊社は本社が北海道なので、冬の積雪による転倒災害を防ぐことに重点を置いて活動しています。
災害未然防止活動はすぐに結果が出るものではないので難しい部分はありますが、災害を起こさないために様々な施策を考え実行しています。
– やり取りをさせていただく中で、御社は安全対策にかなり力を入れて活動しているイメージがありました。そんな中でVRの安全教育を導入した経緯を教えていただけますか?
ダイナックス様:
我々の部署では、新規入職者に対して法令で定められた教育を実施しており、その中で体感機材を昔から使用していました。
その機材が古くなってきたため、VRの教材も含めて更新の検討をしていました。
そんな中、弊社の情報システム部からスペースリーを紹介されて導入検討を始めたという経緯です。

– では、VRを導入するまでは新規入職者の方は体感機材のある場所に行って、災害体験をされていたわけですね。
ダイナックス様:
そうです。新規入職者には必ず受講いただいています。
– スペースリーを導入する際に、他社のVRと比較はされましたか?
ダイナックス様:
スペースリーを導入する前に、他社さんのCG VRを試してみたことがあります。「これはすごいな」と思いましたが、初期導入コストが大きく、限られた予算の中では導入が難しい状況でした。
また、コンテンツもどちらかというと建設業のものが多く、コンテンツを増やしていくごとにコストがかかる部分も難しい点でした。
そこで初期費用が抑えられて、自分たちの現場をVRコンテンツにできるところも魅力的だということで、スペースリーの導入を決めました。
– ご契約いただいている会社様のコンテンツを弊社側で見せてもらう機会もありますが、現場も各社様によって異なりますし、社内ルール等細かい部分はやはり少しずつ違う印象はあります。
ダイナックス様:
他社のCG VRを体感した際「落ちる」などの体験はCGの方が怖いと感じました。
ただ、機械に巻き込まれるなどの手元の作業に関しては、CGだとそこまで怖さを実感できませんでした。
それならば自社で実写VRを作って、過去に発生した災害を体感し、正しい行動を学べるほうが良いと感じています。
また、過去に通常動画で安全対策のコンテンツを作成して公開したこともありますが、VRを実際に体験した結果、より効果的だと感じ導入を決めました。
“怖さ”を伝えるツールとしてVRゴーグルを活用
本人視点の能動的な研修で「従来の研修よりわかりやすい」と85%が回答
– 現在、企画制作はどんな体制で運用されていますか?
ダイナックス様:
基本的には私が制作担当で、他に製造部門の教育担当者に協力していただき二人で企画や撮影などを行っています。実際の設備を使って撮影をしているので、昼休憩で設備が止まっている時など隙間時間で撮影を実施しています。
企画は過去の災害事例等をベースに部署内でVR化するものを選定し、動画の流れを型化したものを参考にシナリオを作成しています。
– 現在どのようなVRコンテンツを制作されて、どのように活用されていますか?
ダイナックス様:
現在は「新規入職者向けのコンテンツ」と「危険箇所が多い現場に入る方向けのコンテンツ」を作成していて、千歳工場と苫小牧工場の2拠点で活用しています。
具体的には、「巻き込まれ」「挟まれ」「火傷」等の過去に発生した災害事例を基に、VRコンテンツを作成しています。
VRは“怖さ”を伝えるツールとして活用しており、受講者に怖いと思ってもらうことで、もし同じような事象が発生した時にも正しい行動をしてもらえるように、現場に出る前に教育を実施しています。
座学なども実施しますが、やはりVRで実際の現場の映像や動きなどを含めて見ていく方が分かりやすいと感じています。
– 一部の教育時間を、座学や体験からVRにシフトされた形ですね。
ダイナックス様:
そうですね。
新規入職者向けのコンテンツは、基礎的な現場の安全教育のために作成しています。
VRコンテンツの中で正しい行動についても説明しており、初めてでも正しい行動ができるようになってもらうことで、災害の未然防止につなげていくことを目的としています。
集合研修の一部で、個別に数分間VRゴーグルで体験をした後に、テストやアンケートに答えてもらう形式です。
また、危険が多い現場に入る方向けのコンテンツは、配置転換等で初めての現場に入る際に視聴してもらいます。
主に切粉(鋭利な切りくず)による切創、高熱による火傷等の怪我のリスクが高い設備をコンテンツ化しています。
また、ラインに異常が起きた時などに、普段の決められた作業以外のことも処置しなければならない瞬間もあります。異常処置の担当が決められていて、その人たちに対しては「異常が起きた時に対処を間違うとこんな怪我につながる」といったVR教育を行っています。
– 実際にVR研修を受講された方の感想などがあれば教えてください。
ダイナックス様:
アンケートで「今までの座学や体感機での教育と比較してどちらの方が分かりやすかったですか?」という質問をしたところ、VRの方が分かりやすいと回答した人が約85%でした。
他にも「実際の現場にいる感覚で臨場感があった」「ゲーム感覚で楽しく学べた」といった感想がありました。
「事故の怖さが伝わったか?」という質問に関しても、約7割が「怖いと感じた」と回答していました。

正直なところ、VRを導入したことによる明確な効果は、他の要因なども関連するため正確には出せていません。
ただ、アンケートの結果も高評価だったことや、受講者自身が手を動かす、自分で操作して動いてもらえることはメリットです。VRは本人が意識を持って動かすものなので、ただ話を聞いているだけ、動画を見ているだけではない、身につく教育ができているように感じます。
1回あたりの動画が1~3分で短く印象に残りやすいところもメリットですね。
また、VRを初めて使う受講者の方も多く、物珍しさから受講者に好意的に受けてもらえる部分もあると思います。
手袋などの小道具を利用したVR撮影の工夫
– 企画制作面で工夫していることや、苦労したポイントはどこですか?
ダイナックス様:
一番苦労したのはやはり撮影方法ですね。
最初はヘルメットの上にカメラを付ける形で撮影していたのですが、手元が見づらくて「一人称視点でもっと手元を映したい」と思い、色々工夫しました。
今は三脚にカメラをつけて、それを胸の前でがっちり固定してちょうどいい位置にカメラが来るよう工夫しています。
手元がうまく映る角度を工夫したり、試行錯誤している形です。

– 御社はヘルメットにカメラを固定したりと、機材を工夫し臨機応変に対応されている印象でした。
ダイナックス様:
他の動画撮影の苦労としては、過去に災害が発生した設備で動画を撮影することが多いのですが、そういった設備は物理的な対策が完了しており、
怪我の発生状況の再現が難しくて苦労しました。
ただ、過去の災害を風化させず、 得られた教訓を伝えることが大切なので、工夫してVRコンテンツを作成しています。
– 機材に指を挟まれてしまうVRコンテンツがありましたが、挟まれる場面はどうやって撮影されたんですか?
ダイナックス様:
挟まれる瞬間は、手袋の挟まれる指を抜いておいて、詰め物をしておいて挟まれたように見せかけて撮影しました。血糊を塗るなど、よりリアルに見せる工夫をしています。
別のコンテンツでは、プラスチックダンボールを壁に見立てて災害が発生した際の設備の状態を再現して撮影しました。
– 工夫して撮影されていると、弊社側でも話題になっていました! 導入から二年ほどですが、VRコンテンツはいくつぐらい制作されましたか?
ダイナックス様:
現在は5つのコンテンツを活用しています。全て過去の災害の再現動画コンテンツとなっています。
例として、異常処置時に電磁弁で操作を行い可動部に挟まれた事例や、 加工後に高温となった製品に触れ火傷した事例を基にしたコンテンツなどがあります。
– 確かに、それはCGでは再現が難しそうなコンテンツですね。
ダイナックス様:
そうなんです。実写VRで制作して良かったと思っています。
– VR制作にかかる工数はどのくらいですか?
ダイナックス様:
作成するコンテンツの内容によっても異なりますが、おおよそ企画は30分~1時間、撮影が30分~1時間程度です。編集は1時間~程度で制作することが多いです。
最初の頃は撮影方法のトライに時間もかかりました。
海外グループ会社にも翻訳したVRコンテンツを展開中
– 今後VR教育を社内的にどう展開していくか、決まっていることがあれば教えてください。
ダイナックス様:
現在、海外グループ会社へのVRの展開を進めていて、ハンガリーのグループ会社では既にVR教育を開始しています。
また、アメリカへの展開準備も進めています。
海外にも同じ設備が入っていますので、基本コンテンツは使い回しができます。すでに展開しているハンガリーでは、コンテンツをハンガリー語に翻訳して使っています。

あとは今後、KYT(危険予知トレーニング)用のコンテンツにVRを活用していければと考えていますね。
KYTを動画と静止画どちらで撮影するかはまだ決まっていないのですが、今後スペースリーさんと相談して決めていければと思います。
– ありがとうございます。では、今後スペースリーに期待することや、実装してほしい機能があれば教えてください。
ダイナックス様:
無理を承知で言うと、動画編集が管理画面で一括できるようになればより使いやすいと思います。
現在は撮影した動画を外部ソフトで編集しているのですが、スペースリー内で編集できるようになればさらに良いなと思います。
– 開発リクエストに回しておきますので、アップデートがありましたらご連絡しますね! 貴重なお話をありがとうございました!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
スペースリーでは今回ご紹介した事例以外にもVRの導入事例が多数ございます。サービスにご興味のある方はもちろん、他社の導入事例について詳細をご希望の方はお問い合わせフォームよりご連絡お願い致します。
導入事例資料をご希望の方はこちらへ
導入事例資料をダウンロード